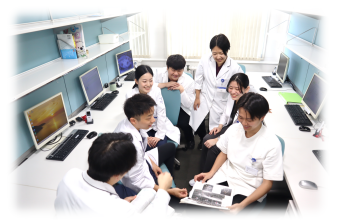お知らせ・ブログ
《指導医ブログ》未来の医療を担う君たちへ。(副院長 Dr.尾﨑)
姫路聖マリア病院副院長、尾﨑琢磨です。脊椎外科を専門としています。気が付けば30余年の医師人生です。最近、以下のような思いを抱いています。
医療の進歩は目覚ましく、10年前の教科書は余り役に立ちません。脊椎外科の領域も例外ではなく、たとえば、腰椎すべり症の患者に対して行う『腰椎固定術』の手術・入院形態も大きく変容しました。
私が研修医の頃は、入院は2-3か月、術後の抗生物質の点滴は1-2週間が当たり前。抜糸までの2週間はベッド上安静。離床後も体幹ギプスを巻いて3か月間装着します。長期臥床による血栓症、感染症、褥瘡は決して珍しくなく、治療を受ける方にも相応の忍耐力が要求される時代でした。
現在の低侵襲手術であれば、術翌日に離床、点滴も翌朝まで、早い人は2週間で退院です。コルセット装着期間も2か月程度に短縮できます。まさに、隔世の感です。
このような進歩は、いかに達成されたのでしょうか?医師単独による新しい手術手技の研究・開発によって齎されたのでしょうか?答えは否です。
まずは、種々の産業界における、金属素材や薬品の開発・改良は必要条件です。精度の高いMRI,CTなくして現在の医療は成り立ちません。そして、DXに象徴される社会の変化も手術の進歩には、大きな影響があると思っています。
よって、医療人は常に変化しないといけません。
ただ、よりよい医療をめざす気持ちは不変です。